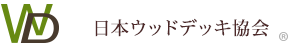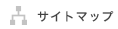ブラジルの光と影 その8
2018年9月26日
「ブラジルの光と影」- その8
長井 一平
「太郎ちゃんとブラジル」
あの寒いロシアで、ワールドカップが行われて、世界の人々がTVに釘付けになりましたね。私はそれを見ていて、ロシアと全く反対の土地で行われた4年前のブラジルのワールドカップの事を思い出しました。
ワールドカップが、ブラジルを思い出させ、そして、ブラジルが太郎ちゃんの事を思い出させたのです。
題して「太郎ちゃんとブラジル」です。
もう40年近い昔の事です。
私は30歳を超したバツイチの中年女でした。
生まれ故郷の淡路島で結婚、離婚した私は、そこから逃げ出して神戸に住み始めました。狭い田舎で離婚した女の生きる道は、その土地から逃げ出すことです。
幸いに大学時代の友達が、神戸で小さな一杯飲み屋の仕事を紹介してくれたのです。
淡路での私の実家は喫茶店をやっていて、結婚する前から家の手伝いでウエイトレスをしていたので、お客さんに給仕する事に慣れていたし、また、私もお客さんといろんな話をする事が好きだったから、渡りに船の良い話でした。
カウンターだけの、5人もお客さんが入れば満席になる小さな店でした。
場所は, JR神戸駅の裏側、そうですね、「国鉄神戸駅」でした。
三宮に比べれば随分と格下。
お客さんもほとんどが港で働く労働者の人々。
けれど皆さん、真面目で、そして貧乏でした。
一本のビールでその日の仕事の憂さを晴らして、また明日、元気に仕事に出かける毎日でした。だから、売り上げも僅かなもの、家賃を払い、酒代金、つまみの材料を払えば、残る利益は、私一人が食べて行けるだけの質素な生活。
しかし、離婚後の生活に疲れ切った私にとっては、毎日が張り切った生活でした。
そんなある日、太郎ちゃんがフラッと店に入って来たのです。
労働者の作業着姿を見慣れていた私は、白い長袖シャツに、黒いズボン、クシャクシャの黒い髪の若い青年の姿を見た時、あまりにも場違いな彼の雰囲気に、お断りしようかと思ったくらいです。
しかし、若い青年特有の、少し青白い細面の顔に、何か暗いものを感じて、「いらっしゃい。どうぞ」と言ってしまったのです。それが、彼との付き合いの始まりでした。
彼は、兵庫県の農業大学の学生でした。生まれは北陸の小さな町とのこと。
初めの頃は、1カ月に1回ほど、おずおずと入ってきて、隅っこの椅子に座り、周りの大人たちの話に聞きいっていました。ビールも一本で、私の作るアテをおいしそうに食べていました。幸いに、当時の「所得倍増政策」そして「東京オリンピック」景気のお陰で、人々は、朗らかで陽気で、私のお店も連日満員で、忙しく楽しく過ごしていました。
しかし、週末はお客さんも来なくなり、いつも誰かと話したい私は、時間つぶしに暇を持て余していました。
まるでそれを見抜いた様に、彼はその時間帯にやって来たから、私は持て余した時間と話題を彼にぶつけ、また、彼も子供の頃の話、両親の話、何故、北陸から神戸に出てきたかの話、などをする様になりました。
「僕の高校時代の終わりころ、お袋がガンで急死したんです。
それから間もなく、親父は15歳ぐらい年下の女性と再婚したのです。
彼女は、服装、生活などに派手な性格で、家の中の生活でも、女性経験のない僕を挑発する様になりました。
男の本能を掻き立てられる苦しい日々のある日、友人に誘われて、それまで行った事のない神戸を訪問しました。
友人の知り合いがブラジルへ移住するから、その見送りでした。
送る方も送られる方も、甲板と岸壁に別れて、たった一本のテープの端と端を握りあって、大声で叫んでいる。
「がんばれよ!」、「手紙くれよ!」「お袋を大事にな。。!」
銅鑼がバンバン打たれる。
船に上がるタラップが外される。
興奮が一挙に高まる。
汽笛が、「ボア―ボア―」と鳴る。
その頃には、あのテープは千切れて、海の藻屑となっているが、甲板の、岸壁の誰も、その端切れを離そうとしない。
そして、「日本よ、さようなら。。」と告げる様に、汽笛が、「ボー、ア―」と聞こえる頃には、船は遥か向こうに消えつつあった」。
「僕はそれを見ていて、身体中の血が逆流する様な興奮に駆られました。
僕が、どの様にして逃げ出そうかと考えていたあの薄暗い、陰気な家を飛び出して、ブラジルと言う外国の地へ人々は飛び出している。
ブラジルって、一体どんな国なのだろうか?
そこは、僕が逃げ出したいと願っているあの田舎の、そして日本よりも、素晴らしい場所、国なのだろうか?。僕は夢中になって調べました。
そして、その夢をかなえる方法が、農業を勉強して、農業移住者になる事だと知りました。
だから、生まれ故郷を飛び出して、神戸の農業大学に入ったんです。
今年1年で卒業します。そして、農業移住者のヴィザを取って、移住の準備をします。」
「康子さん。ブラジルって、素晴らしい未来の国です。
何よりも国が大きい。日本の24倍もある。
その大きな国で大豆栽培が始まっています。
大豆はこれからの世界食糧になります。
それを栽培して、世界の人々の為に尽くしたいのです。」
お酒が入って気分が高まってくると、その若くて輝く肌、そのほっぺたが高揚してピンク色になってくるのです。黒い目もキラキラ光る。
それはきれいなものです。
心が純粋だから、余計輝くのでしょう。
その美しさを目の前にすると、私の独り身の体が疼いて、自分の年齢も考えずに引きずり込まれそうになる事が、何度もありました。
それほどの親しい話をしていても、私たちは、僅か1年足らずの付き合い。
そんな短期間にも関わらず、彼が自分の過去や、後妻の母親との葛藤を隠すこともなく語り、そして、ブラジルへの将来への夢を私にぶつける様になったのは、それする相手が居なかったからでしょう。
そして私も昔の喫茶店時代の経験があったから、彼の話を親身になって聞いて上げれる様になってたのでしょう。
「ねえ康子さん。貴女は離婚して一人、まだ若いじゃないか。
僕と一緒にブラジルへ行って、新しい人生を開こうよ!!」。
「馬鹿ね、何を言ってるの。貴方はこれから大きな人生を目指して頑張る人。
私は、人生の半分が終わった只の女。
貴方は、同じような年齢の若い女性を見つけて、二人で夢を実現して行きなさい」。
そう言った時、彼の右手が私の頬をバシッと打った。
「痛い!」と思うより、体中に感動がズーンと走りました。
自分がした事に気が付いた彼は、「康子さん。ゴメン」と泣きそうな顔をして謝りました。
それからしばらくして、彼の卒業の日が近づいて来ました。
ある日の午後、まだ店を開ける前に、太郎ちゃんは、きちんと学生服を着て、挨拶にやって来ました。
「康子さん。いろいろ有難うございました。
取り合えず、実家に戻り、ブラジル行きの準備をします。
本当にありがとう御座いました。」
1年前の少し青白かった顔もふっくらとして、目がキラキラとしていました。
私は、まるで恋人と別れる様に、しんみりとなりました。
そして、バツイチ女の気丈夫さを見せてやろうと、心を鬼にして話しました。
「太郎ちゃん。これからの人生の道が決まって良かったね。
私も、太郎ちゃんが居なくなるから、この店を閉めて生まれ故郷の淡路へ帰るわ。
だから、私の事なんか忘れて、素晴らしい将来に挑戦して行ってね。
またまた、そんな悲しい顔をしている。
ダメダメ,何時もどうりの明るい笑顔を見せてよ。
そして、あのブラジルの夢を追いかけていってね。」
私の心の中に湧き上がってくる、寂しさと、恋しさと、別れの悲しさ。
あの時に頬をぶたれた痛みは、「きれいな痛み」として、身体に染み付いている。
さあ私も、この別れを機会に、また新しい恋愛を探して、これからの新しい人生に挑戦して行こう。
日本の春、桜が満開になった頃でした。
神戸の六甲下ろしの風がさっと降りてきて、満開の桜の花びらを散らしていました。
「太郎ちゃん、さようなら。いつかまた、会える日があることを期待していますよ」。
終わり