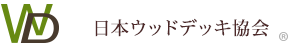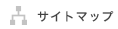ブラジルの光と影 その12
2020年3月24日
ブラジルの光と影 - その12 長井 一平
「青春 真っ只中」-古き良きブラジル。
今、ブラジル(サンパウロ)は、夏の始まり。
そして、今週末からカーニバルが始まる。
まだ陽は高いのに、遠くから、腹の底に響く様な太鼓の音が聞こえてきます。
私は、いつもの病院で、年相応の病気の高血圧と糖尿病の検査をやってもらっていました。
「3か月ごとの検査」と担当医者から命じられているのに、あまり愉快な事でもないので、キチンと決めたように診断にやって来ていなかった。
その待ち時間の間、傍の小さなテーブルに置いてある雑誌に、ふと手が伸びました。 週刊誌大の薄い手ごろな雑誌に『第三文明』の文字。
「確か創価学会発行の雑誌だったな」50年以上の昔の、学生時代のかすかな記憶が浮かび上がってくる。
興味にひかれて、表紙をめくる。
すると、いきなり、地下鉄の電車の中の壁やドアーに吹きつけられた黒いスプレー、骨太の殴り書きの白黒写真が現れる。
見事なくらいな真っ黒なペンキの落書きだ。
明色の背面に、黒色でABCや〇や三角を乱暴に吹き付けるのは、社会の底辺の住民の、仕返しと一種のストレスの発散だろう。
真っ白なビルの壁に、このストレスが吹き付けられているのは、サンパウロの下町でも、よく見かける。
ハイパーインフレや、路上のピストル強盗など、国の経済が悪くなり、社会不安が高まった時に、黒い吹き付けは町中に暴れ回ったと覚えている。
そして、セントラルパークで、黒人が白人女性をレイプする事件が報道されたのも、あの頃だったな、、と、かすかな記憶も呼び戻ってくる。
思いもかけず、40年、50年前の若いころに引きずりこまれながら、この写真の投稿者のエッセイに目が移る。
「青春の真っ只中の1981年1月、目標のニューヨークへの移住がかなった。。。。。。片道チケットを手に入れて、アメリカへ飛んだあの日から38年。日本を出たからこそ、日本の美しさにも気付くようになった。。。。。
思い切り駆けぬけた青春時代だった」。
「『青春の真っ只中』、『思い切り駆け抜けた』、、、なんて素晴らしい言葉なんだ。
俺にもそんな時期があったな。。。」
私は、自分が何処にいて、何をしているのか、すっかり忘れてしまって、45年前のブラジルの東北地帯の古都、RECIFE(レシーフェ=隷子笛)の思い出にハマりこんでいた。
大学2年生の倦怠な或る日、私は外務省が若者たちの海外進出の目を開けさせる為に、南米の諸国を知る機会を与えているのを知った。
多くの大学で南米研究会が創設されて、毎年10人の学生達が試験を受けて、選ばれて移住船に便乗して、南米の各国に「実習生」という名前で海外体験をしている事を知った。
当時の海外体験の国は、北アメリカと南アメリカしかなかった。
北アメリカは、フルブライト留学生の如く、敗戦国の若者にアメリカを教える為に、日本の家庭も裕福で、学生も英語が流暢な、将来の優秀官僚養成の為の様な制度だったが、南アメリカへの若者選抜は、将来移住を望む、農業専攻の学生が
多く応募していた。黒い学生服のボタンをキチンと締めて、オッス、オッスと挨拶している様な硬派の若者たちだった。
しかしそうした硬派だけではなく、商学部、経済学部など、オッス組からみれば軟派の文化系の学生も参加していた。私もその一人だった。
受け入れ国のブラジルも、農業国から工業、商業国への発展を意図していたから文科系の実習生の受け入れをしたのだろう。
しかし、問題はブラジルの実習先だった。農業学生は、農家に潜り込み、耕しておればよい。
しかし、文化系学生は、どこで実習すればよいのか?
言葉も十分でなく、仕事環境にも無知な日本のひ弱な学生が暮らす場所は、何処か??。
文科系は皆が皆、サンパウロやリオの日本人経営の会社に1年足らずの短期の採用を頼み込んだ。そして私は?? 50年前の後進国のブラジルの、さらに後進地域で貧困の町、RECIFE(レシーフェ)のブラジル人経営の、300人の工員が働く紡績会社に潜り込む事に成功した。
それを知って、仲間達は驚いた。皆、若いから、ブラジルの全く異なる環境で自分の力を試してみたかったが、言葉が話せないことが、最大の問題だったから、それぞれの伝手を求めて、日系会社に職を決めて行った。
それを横目で見ながら、私は主張した。
「ブラジルにまでやってきて、日本人経営の会社でブラジルが学べるのかい? 俺は嫌だ。日本人がいない、ブラジルの奥地に入るよ。」仲間は問い返した。
「お前はブラジル語を十分に話せるのかい?」「いや、ダメだ。
しかし、習うより慣れろ、だ。お天とうさんとコメの飯は、何処でもついて回るよ」。
サンパウロから3000km北の南緯8度の熱帯地。電話通話も簡単ではない。
病気になれば?。
事故が起これば?。
仲間は心配してくれた。日本まで1か月かかったが郵便が届いた。それで十分だ。
この様にかなり無理したツッパリを張ったのには、私なりの理由があった。
外務省の試験に合格して、10人の一人に決まった時、どの様なブラジル生活を
作り上げようか、と、一人考えた。「皆の様に、日系社会の中で1年を過ごそうか?それとも全く奥地に入り、ブラジル人と一緒に暮らそうか?。」
どちらも、良い点、悪い点があった。
その悩みの或る日、ブラジルの歴史で、
「東北ブラジルの歴史と発展」を読んだ。
「ポルトガル人によって発見されたブラジルの南部地域は、温暖な気候や肥えた土壌に恵まれて、コーヒ栽培が盛んになった。
しかし、東北ブラジルの土壌は、その暑さの為に、コーヒ栽培は不適だった。
そして、産業革命によって飛躍的に発展した綿織物への原綿の需要が世界的に爆発した。南緯8度の天候は、綿栽培に最適な場所、その地へ、ポルトガルからチャレンジ精神に燃えた若者達が、未知の大陸へ向かっていった。
綿栽培の過酷な労働は、アフリカから輸入された黒人ドレイ達だ。
そして、何百人という奴隷たちが住む農園のオーナーは、青春を未知の世界に賭けた若者達であり、彼らのベッドには、年頃に育った黒い娘達が呼ばれた。
娘たちの黒い見事な肢体、白人の白い容姿と理知的な風貌、それらが交じりあわされて混血の傑作と思われる様な新しいブラジル民族が生み出されていった。
黒人は、生本来、奔放な本能を持つ。それに溺れる毎に、若者たちの家族は、大きくなって行った。」
RECIFEには、春秋はなく、乾季と雨季だけ。
そして乾季の終わりころ、「ピー、ピー」と鳴る単調な草笛の音が町中に流れる。
煎りピーナツ売りの子供達の草笛だ。
おっかさんに言われて町に出る裸足の貧しい子供たちだ。
まるで、奴隷の子供たちの様だ。
それを見ている内に、このRECIFE(レシーフェ)の町に,「隷子笛」という漢字を当てはめた。
東北ブラジル、そして、その中心都市の隷子笛は確かに貧しかった。
綿花、綿糸などのモノカルチャー経済のみが、地域の経済を支えていたからだ。
一方、日本では東京オリンピックがあり、経済大国に走り出したキンキラ金の時代だった。
日本と全く異なる国で、その世界で彼らと一緒に住むことによって、日本には見られない考え方がある事に気付いた。
「幸せとは、経済的成功によってのみ、得られるものなのか」。
私の周囲の人たちは、確かに貧しかった。
しかし彼らはその貧しさを恥じておらず、逆に、朗らかだった。キリスト教の信仰があることは確かだ。
しかし、アフリカの奴隷をルーツとする人々にとって、日本人の様に国民が一つに纏まって先進国に進んで行くことは、夢物語だった。
「俺たちはこれでいいのだ」と自分達の気持ちを正直に日本から来た大学生に話し、その代わり、自分達の生活を隅々まで見せてくれた。
それは、分相応「無理をしない」と言う生き方だった。
自然条件、国民の能力、それらを冷静に分析していた。
その時から、「俺の将来は、ブラジルだ」と、日本を出た時には考えもしなかった思いに捕らわれ始めていた。
お金はなかったが、仲間たちに囲まれて、夢中で楽しく暮らした1年だった。
しかし帰国する日は近づいて来た。
当日、私は一つしかない紺の団員服と赤いネクタイを締めて会社に行った。
下宿の黒人のおばさんが「オージ,ムイント ボニート」と歯の抜けた口を開けて、カラカラと笑った。
「今日のお前は、キレイだよ」と誉めてくれているのだ。
会社に着いた。すると顔見知りの仲間達が、20人はいただろうか、ワーと私を取り巻いた。
「驚くなよ、明日がお前の出発だ、皆がカンパして土産物を買ったんだよ」。
東北ブラジルの土人形、ヤシの実のピンガなどが包み込まれていた。
その瞬間、涙があふれて来た。
「オブリガード」の言葉が出て来ない。
ヴァスコがいる、オズワルドが笑っている、何も見えない。
「隷子笛を好きになってくれて有難う。大学卒業したら、またブラジルへ来てくれ。皆で待ってるからな」。
「有難う、皆さん。 さようなら、隷子笛、そして、さようならブラジル。私は必ず戻って来ます。」
受付が私を呼んでいる。「ああそうだ。ここは病院なのだ。糖尿病と高血圧の検査なんだ。」 腹立たしい老人病だ。
あの熱い日々は、消えてしまったのだろうか。いや、まだ俺の体の奥で、どくどくと脈打っている。思い出すことが大事なのだ。熱い血をいつまでも持ち続ける事が、大事なんだ。」
以上
次回予告「中年、真っ只中」-稲盛和夫さんとの年月。
次々回予告「まだ駆け続ける老年」―トランプ大統領のアメリカ。
2020年2月24日